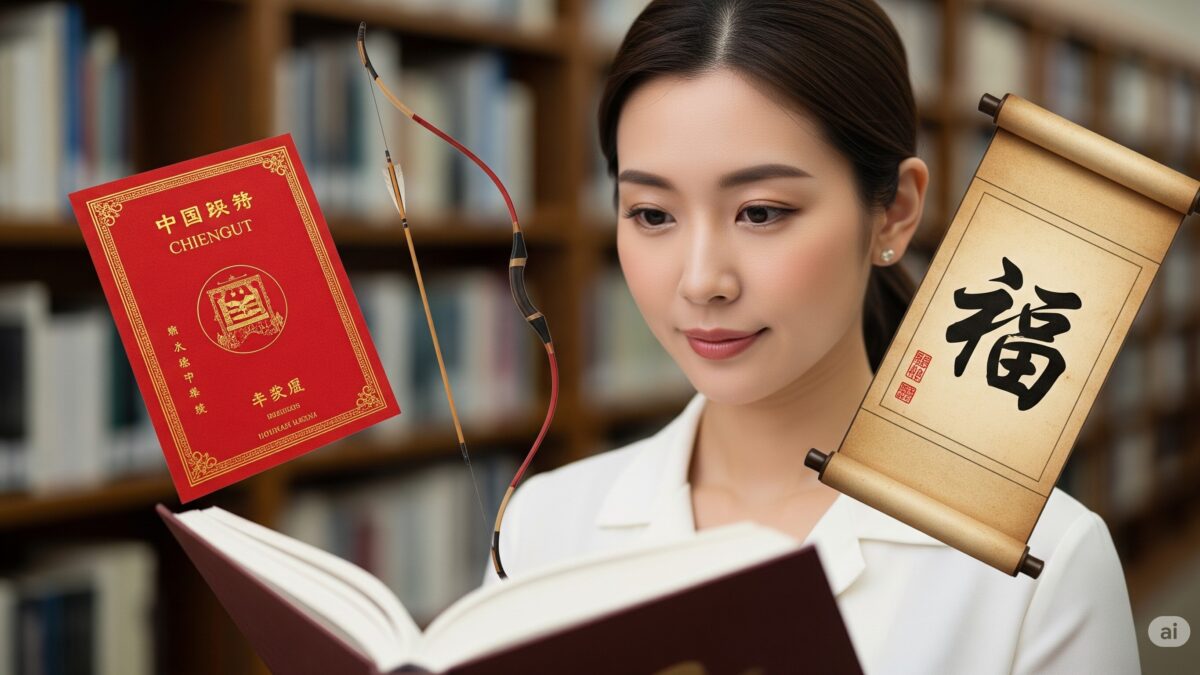
【衝撃の事実】中国 苗字TOP3は3億人⁉︎ ランキングと歴史の謎に迫る
中国の方と名刺交換をしたとき、「また王さんだ」「李さんは本当に多いな」と感じたことはありませんか?
日本には10万種類以上もの苗字があると言われる一方で、なぜ中国では特定の苗字ばかりを耳にするのでしょうか。そして、その苗字には一体どんな歴史が隠されているのでしょう。
この記事では、そんな中国 苗字にまつわる素朴な疑問から、歴史や文化に根差した深い謎まで、どこよりも分かりやすく徹底解説します。
●この記事を読んでほしい人
- 中国で一番多い苗字が何か知りたい人
- 日本と中国の苗字文化の違いに興味がある人
- かっこいい・珍しい苗字の由来や歴史を知りたい人
●この記事を読むメリット
- 最新の中国苗字ランキングTOP10がわかる
- なぜ特定の苗字に人口が集中しているのか理由がわかる
- 「王」「李」「張」など有名な苗字の壮大な起源がわかる
- 夫婦別姓など日本と違う苗字の常識がわかる
- 「死」姓など珍しい苗字や複姓の面白い知識が身につく
単なる知識を超えて、中国の歴史と文化の面白さに触れる旅へ、さあ出発しましょう。
中国の苗字はなぜ少ない?TOP10と分布図

- 最新版!人口が多い苗字ランキングTOP10
- 人口の8割以上が100姓?驚きの集中度
- 「北の王、南の陳」地域で違う苗字の分布
- 『百家姓』は人口順ではない?政治が作った順位
- 夫婦別姓が当たり前?日本と違う苗字の常識
最新版!人口が多い苗字ランキングTOP10
中国で一番多い苗字って何だろう?と疑問に思ったことはありませんか。日本にはたくさんの苗字がありますが、中国の状況は少し違うようです。
さっそく、どの苗字が最も多いのか、最新のデータに基づいたランキングを見ていきましょう。
まずは結論から!TOP3は「王・李・張」
中国で最も多い苗字は、長年にわたって「王(おう)」「李(り)」「張(ちょう)」の三つが占めています。この三大姓だけで、地球上で最も大きな同姓集団を形成していると言われるほど、その数は圧倒的です。
驚くべきことに、「李」さんや「王」さんに至っては、それぞれ1億人近くもいると推計されています。日本の総人口に匹敵するほどの人が、同じ苗字を名乗っていると考えると、その規模の大きさが想像できるのではないでしょうか。
さらに、「劉(りゅう)」「陳(ちん)」を加えた五大姓になると、中国の全人口のおよそ3割を占める計算になります。
中国の苗字ランキングTOP10一覧
それでは、10位までのランキングを、中国語の発音(ピンイン)と日本語の音読みと合わせて紹介します。
1位:李 (Lǐ / リ)
2位:王 (Wáng / オウ)
3位:張 (Zhāng / チョウ)
4位:劉 (Liú / リュウ)
5位:陳 (Chén / チン)
6位:楊 (Yáng / ヨウ)
7位:黄 (Huáng / コウ)
8位:趙 (Zhào / チョウ)
9位:呉 (Wú / ゴ)
10位:周 (Zhōu / シュウ)
いかがでしたでしょうか。もしかしたら、あなたの知り合いの中国人の方と同じ苗字があったかもしれませんね。
このランキングを見ると、いかに特定の苗字に人口が集中しているかが分かります。では、なぜ中国ではこれほど少数の苗字が大多数を占めるようになったのでしょうか。次の項目で、その秘密に迫っていきます。
人口の8割以上が100姓?驚きの集中度
先ほどのランキングで、特定の苗字に多くの人が集まっていることが分かりました。しかし、その集中度は私たちの想像をはるかに超えるレベルかもしれません。
信じがたいかもしれませんが、中国では上位100種類の苗字だけで、全人口の実に8割以上、約87%を占めていると言われています。
つまり、10人いれば8人か9人は、誰もが知っているようなメジャーな苗字を名乗っている計算になります。なぜ、これほど極端な人口集中が起こったのでしょうか。
歴史の中で苗字が淘汰された?
その背景には、中国の長い歴史が関係しています。歴史を紐解くと、中国にはかつて2万4000種類以上もの苗字が記録されていた時期がありました。
しかし、現在実際に使われている苗字の数は、約6000種類にまで減少しています。
長い年月をかけて、漢民族が文化の中心となる過程で、周辺の少数民族が漢民族風の苗字に変えたり、複雑で読みにくい苗字が、よりシンプルで一般的な苗字に吸収されたりしていきました。
言わば、歴史の大きな流れの中で、苗字の「淘汰」と「統合」が繰り返された結果が、現在の姿なのです。
「張偉さん」が多すぎる?同姓同名の問題
このように苗字の種類が少ないと、社会ではある問題が起こります。それは「同姓同名」の人が非常に多くなってしまうことです。
例えば、中国で最も多い名前の一つに「張偉(ちょう い)」という名前があります。日本でいう「佐藤太郎さん」のようなイメージかもしれませんが、その数は桁違いで、全国に何十万人もの「張偉さん」がいると言われています。
学校のクラスに同じ名前の子が何人もいたり、社会に出てからも人違いが起きやすかったりと、生活の中で不便な場面も少なくないようです。
この苗字の集中度は、中国という国の成り立ちを映す鏡のようなもの。数千年の歴史が生んだ、非常に興味深い文化現象と言えるでしょう。
「北の王、南の陳」地域で違う苗字の分布
中国の苗字は、国内で均等に分布しているわけではありません。むしろ、地域によってかなり大きな偏りが見られます。その特徴をひと言で表す、こんな言葉があるのをご存知でしょうか。
「北の王(おう)、南の陳(ちん)」
これは、中国の北部では「王」姓が、南部では「陳」姓が特に多いことを示す象徴的なフレーズです。なぜ、このようなはっきりとした地域差が生まれたのでしょうか。
北方の支配者?政治の中心地に多い「王」姓
中国の北部、特に北京や天津を含む黄河流域は、古くから多くの王朝が都を置いた、中国文明の中心地でした。
「王」という苗字は、その多くが周王朝時代の王族の末裔に由来すると言われています。国の政治を動かしてきた中心地で、高貴な出自を示す「王」姓が広く根付いていったのは、自然な流れだったのかもしれません。現在でも、北部の16の省や市で最も多い苗字は「王」姓となっています。
南へ、南へ。移住の歴史を物語る「陳」姓
一方、南部に多い「陳」姓の背景には、人々の大規模な南下移住の歴史があります。
過去、中国では北方の地域で戦乱や政治的な混乱がたびたび起こりました。そのたびに、多くの人々が安住の地を求めて、豊かな土地が広がる南の沿海部へと移り住んでいったのです。その移住者の中に「陳」姓を持つ人々が多く含まれていたため、広東省や福建省といった南方で「陳」姓が栄え、広がっていきました。
「李」や「張」はどこに多い?
もちろん、他の苗字にも地域的な特徴があります。
例えば、中国で最も人口が多い「李」姓は、国の真ん中あたりから南西部にかけてのエリアに多く見られます。また、国際的な大都市である上海で最も多い苗-字は「張」姓です。
このように、苗字の分布図は、まるで中国の歴史地図のようです。一つ一つの苗字が、その一族がたどってきた長い旅の道のりや、根付いた土地の記憶を今に伝えているのです。
『百家姓』は人口順ではない?政治が作った順位
中国の苗字について調べると、必ずと言っていいほど目にする『百家姓(ひゃっかせい)』という古典があります。多くの苗字が並んでいるため、昔の人口ランキングだと思っている方も少なくありません。
しかし、実は『百家姓』の順番は、人口の多さとは全く関係がないのです。では、一体何に基づいて、あの順番が決められたのでしょうか。
昔の子供が使った「音読の教科書」
『百家姓』が作られたのは、今から1000年以上も前の北宋時代です。これは、当時の子供たちが文字を覚えるために使った、一種の教科書でした。
「趙(ちょう)・銭(せん)・孫(そん)・李(り)……」と、四文字ずつのリズムの良い文章になっており、声に出して暗唱しやすいように工夫されています。日本でいう「いろは歌」のようなもの、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
冒頭の4文字に隠された政治の序列
『百家姓』が人口順でないことの最大の証拠は、冒頭に並ぶ四つの苗字「趙・銭・孫・李」に隠されています。この並びは、当時この本が作られた地域の、政治的なパワーバランスを色濃く反映しているのです。
- 趙 (Zhào):当時、中国全土を支配していた宋王朝の皇帝の苗字でした。最高権力者への敬意を示すため、一番最初に置かれています。
- 銭 (Qián):『百家姓』が編纂された呉越国(現在の浙江省あたり)を治めていた王様の苗字です。
- 孫 (Sūn):その呉越国の王様の正妃(奥様)の苗字でした。
- 李 (Lǐ):呉越国の隣国であった、南唐国の王様の苗字です。
このように、人口の数ではなく、当時の政治的な権威の高さに基づいて順番が決められていたのです。
『百家姓』は、単なる苗字のリストではありません。苗字というものが、時の権力や社会構造と、いかに深く結びついていたかを物語る、貴重な歴史の証人なのです。
夫婦別姓が当たり前?日本と違う苗字の常識
日本では結婚すると、夫婦のどちらかが苗字を変えるのが一般的ですよね。しかし、お隣の中国では、苗字に関する常識が大きく異なります。
結論から言うと、中国では夫婦がそれぞれ結婚前の苗字を名乗り続ける「夫婦別姓」が当たり前です。法律で定められているだけでなく、社会の慣習として深く根付いています。
結婚を機に苗字を変えるという手続き自体が存在しないため、女性は結婚後も自分の姓をそのまま使い続けます。
子供の苗字はどうなる?変わりゆく伝統
では、生まれてくる子供はどちらの苗字を名乗るのでしょうか。
伝統的には、子供は父親の苗字を継ぐのが一般的でした。しかし、近年ではその考え方にも変化が見られます。母親の苗字を子供に継がせる家庭も増えており、その割合はおよそ12対1にまでなっているというデータもあります。
両親の苗字を合体?新しい苗字の誕生
さらに、もっとユニークな動きも出てきています。それは、父親と母親、両方の苗字を組み合わせて、子供に新しい苗字を名付けるという方法です。
例えば、お父さんが「張」さん、お母さんが「王」さんだった場合、子供の苗字を「張王」とするといったケースです。
この背景には、かつての一人っ子政策の影響があります。両家にとって一人しかいない子供や孫に、双方の家の血筋を残したいという願いが、こうした新しい命名の習慣を生み出しているのです。
夫婦別姓という変わらない伝統がある一方で、子供の苗字のあり方は社会の変化と共に柔軟に姿を変えています。中国の家族観が垣間見える、非常に興味深い文化と言えるでしょう。
英雄から神話まで!面白い中国の苗字の起源

- 王家の血筋を引く「王」姓の多様なルーツ
- すももの木が由来?哲学者・老子の「李」姓
- 弓矢の発明者が祖先?「張」姓の壮大な物語
- 諸葛、欧陽など、かっこいい二文字の複姓
- 「死」姓も実在?少数民族の珍しい苗字たち
王家の血筋を引く「王」姓の多様なルーツ
ここからは、中国の苗字が持つ、面白くて壮大な起源の物語をいくつかご紹介します。
まずは、ランキングでも上位に入る「王(おう)」姓です。「王」という漢字が「キング」を意味することからも想像できるように、この苗字のルーツは中国史の様々な王族に繋がっています。
周王朝の王子様がルーツ?
「王」姓の最も主要な起源は、古代の周王朝(紀元前1046年頃~)の王族である「姫(き)」姓に遡ります。
当時、王族の子孫や分家した人たちが、国が滅びたり王位を失ったりした際に、自分たちの高貴な出自を忘れないようにと「王」を名乗るようになりました。
特に有名なのが、周王朝の王子であった姫晋(きしん)という人物の物語です。王への直言が原因で身分を剥奪された後、姫晋の子孫が「王家」と呼ばれたことから、「王」姓を名乗り始めたと伝えられています。
中国史を動かした二大名門「王氏」
姫姓をルーツとする「王」氏の一部は、戦乱を逃れて移住し、やがて中国の歴史に絶大な影響力を持つ二つの名門氏族を形成しました。
一つは山西省の「太原王氏(たいげんおうし)」、もう一つは山東省の「琅琊王氏(ろうがおうし)」です。この二大王氏は、後漢から唐の時代にかけて、多くの優れた政治家や文化人を輩出し、名門としての地位を確立しました。
このように、「王」姓は単一の血筋ではなく、中国の歴史における「王権」という概念そのものに根ざした、複合的で格式高い苗字なのです。
すももの木が由来?哲学者・老子の「李」姓
中国で最も人口が多い苗字、「李(り)」。その起源には、まるで物語のような美しい伝説と、王朝の歴史が深く関わっています。
「李」という漢字は「すもも」の木を意味しますが、一体なぜ、果物の名前が苗字になったのでしょうか。
命を救った「すももの木」の伝説
「李」姓の最も有名な起源譚は、殷王朝の時代に遡ります。
もともと、この一族は法律を司る役職名にちなんで、道理の「理」という苗字を名乗っていました。しかし、暴君として知られる紂王の時代、一族の理徴(りちょう)という人物が王の怒りを買って処刑されてしまいます。
理徴の妻と幼い息子は命からがら都を逃れ、飢えに苦しむ中、すももの木の実を食べて命をつなぎました。
このすももの木への感謝を忘れないため、親子は苗字を「理」から、木へんに子と書く「李」へと改めたと伝えられています。この物語は、「李」姓が持つ正義と再生のイメージの源泉となりました。
唐王朝が生んだ「天下の李」
伝説もさることながら、「李」姓が爆発的に広まった最大の理由は、歴史上の大帝国「唐王朝」の存在です。
唐(618年~907年)を建国したのが李氏の一族だったため、「李」は国の姓(国姓)となりました。当時の皇帝たちは、手柄を立てた家臣や将軍、同盟を結んだ異民族の長などに対して、最大級の栄誉として国姓である「李」の苗字を授けました。
この政策により、「李」姓は中国全土、さらには国外にまで広がり、「天下の李」と称されるほどの巨大な姓氏集団へと発展したのです。
また、道教の始祖である哲学者・老子の本名が李耳(りじ)とされることも、「李」姓に深い文化的権威を与えています。
弓矢の発明者が祖先?「張」姓の壮大な物語
「王」「李」と並び、中国三大姓の一つに数えられる「張(ちょう)」。この苗字には、一つの偉大な発明にまつわる、英雄のような壮大な物語が秘められています。
その起源は、伝説上の始祖である黄帝(こうてい)の孫にまで遡ると言われています。
弓矢を発明した英雄「揮」
「張」姓の祖先とされるのは、黄帝の孫にあたる揮(き)という名の人物です。
伝説によると、揮は夜空に輝く星々の配置から着想を得て、「弓矢」を発明したとされています。狩猟や戦いの方法を根本から変える、画期的な発明でした。
この大きな功績により、揮は弓を管理する「弓正(きゅうせい)」という官職に任命されます。
「弓を張る」様子から生まれた苗字
「張」という漢字をよく見てみてください。「弓」へんに「長」いと書きます。この漢字は、まさに弓を長く引き絞り、矢を放とうとする様子を表しているのです。
黄帝は揮の偉大な功績を称え、その子孫に、弓矢の発明を象徴する「張」という姓を与えたと伝えられています。
「張」という苗字は、単なる名前ではありません。人類の歴史を変えた革新的な技術と、その発明者に与えられた名誉の記憶が刻まれた、力強く勇ましい物語をその内に秘めているのです。
諸葛、欧陽など、かっこいい二文字の複姓
三大姓の壮大な物語はいかがでしたでしょうか。しかし、中国の苗字の面白さは、人口の多いものだけに留まりません。
数は少ないながらも、漢字二文字で構成される「複姓(ふくせい)」は、その独特の響きから「かっこいい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
三国志の英雄たちを思い浮かべる苗字
「複姓」と聞いて、日本の歴史や三国志が好きな方なら、ピンとくる名前があるかもしれません。
例えば、天才軍師として名高い「諸葛亮(しょかつりょう)」の「諸葛(しょかつ)」。魏の礎を築いた「夏侯惇(かこうとん)」の「夏侯(かこう)」。そして、晋王朝を建国した一族である「司馬懿(しばい)」の「司馬(しば)」。
いずれも歴史物語を彩る英雄たちの苗字であり、どこか格調高い響きを持っています。
その由来は地名や役職名から
こうした複姓は、どのようにして生まれたのでしょうか。その起源は様々です。
先ほどの「司馬」は、もともと軍馬を管理する長官という「役職名」でした。また、「上官(じょうかん)」という複姓は、身分の高い役人が住んでいた「地名」に由来します。
その他にも、漢民族以外の民族の名前を、漢字の音を当てはめて作った複姓も存在します。
現代で最も多い複姓は「欧陽」
歴史的な響きを持つ複姓ですが、もちろん現代でも使われています。
現在、中国で最も人口が多い複姓は「欧陽(おうよう)」で、その数はおよそ111万人にのぼります。
一文字の苗字が大多数を占める中国において、複姓は珍しく、特別な存在感を放っています。その歴史的な背景や物語性が、人々を惹きつける魅力になっているのかもしれません。
「死」姓も実在?少数民族の珍しい苗字たち
中国には、三大姓や複姓のほかにも、私たちの常識を覆すような、非常に珍しい苗字が存在します。
見出しにもある「死」という苗字。縁起が悪いと感じるかもしれませんが、この苗字は実際に中国で使われています。その起源は、南北朝時代に少数民族が使っていた長い苗字が、漢字一文字に簡略化されたものと考えられています。
「柴米油塩」ぜんぶ苗字に?
驚くような苗字は「死」だけではありません。
中国には、昔の生活に欠かせなかった七つの品々、「柴(さい)・米(まい)・油(ゆ)・塩(えん)・醤(しょう)・酢(さく)・茶(ちゃ)」が、すべて苗字として存在しているのです。
さらには、「難(なん)(困難)」といった、通常は名前に使われないような言葉も苗字として受け継がれています。これらの珍しい苗字は、特定の歴史的出来事や言語的特徴が、現代まで生き残った「歴史の化石」のような存在です。
少数民族が持つ多様な苗字文化
こうした珍しい苗字の多くは、漢民族以外の55の少数民族の文化にルーツを持っています。
例えば、清王朝を建国した満州族は、王朝が滅びた後、多くが漢民族風の苗字に変えました。元の一族の名前の意味や音に合わせて、「金(きん)」や「関(かん)」といった苗字を名乗るようになったのです。
一方で、チベット族やウイグル族のように、伝統的に「姓」という概念を持たない民族もいます。個人の名前に父親の名前を続ける形で自分を名乗るなど、漢民族とは全く異なる命名文化を育んできました。
このように、珍しい苗字や少数民族の命名文化に目を向けることで、中国という国が、いかに多様な民族と文化が入り混じってできているかが、より深く理解できるのではないでしょうか。
まとめ:中国の苗字から見える歴史と文化

記事のポイント
- 上位100姓で全人口の8割以上を占める
- 最も多い苗字は「王」「李」「張」の三大姓である
- 北部では「王」姓、南部では「陳」姓が多い傾向がある
- 古典『百家姓』は人口順ではなく政治的な序列を反映
- 結婚後も夫婦が別々の姓を名乗るのが一般的だ
- 「李」姓は命を救ったすももの木に由来するという伝説がある
- 「張」姓は弓矢の発明者に由来するとされる
- 「諸葛」や「欧陽」など二文字のかっこいい複姓も存在する
- 「死」や生活必需品の「油」「塩」といった珍しい苗字も実在する
- 歴史の中で苗字は淘汰され種類が大幅に減少した
総括
この記事では、人口の多い苗字ランキングから、その壮大な起源、そして日本とは異なる夫婦別姓の文化まで、奥深い中国の苗字の世界を多角的に掘り下げてきました。
「王」「李」「張」といった、それぞれが一億人近くにもなる苗字に秘められた英雄譚や伝説には、ロマンを感じずにはいられません。また、上位100姓に人口の8割以上が集中しているという驚きの事実や、「北の王、南の陳」といった地域差は、中国という国の壮大な歴史スケールを物語っています。
一つの苗字が、民族の移動、王朝の栄枯盛衰、そして人々の願いを映し出す歴史の証人であることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。次に中国の方の名前を目にしたとき、その一文字の裏にある何千年もの物語に、思いを馳せてみてください。
この記事が、あなたの知的好奇心を満たし、中国の苗字に対する見方を豊かにする一助となれば幸いです。

