
相次ぐ「日本企業中国撤退」の報道。しかし、その実態は…?
「日本企業の中国撤退が加速している」というニュースを毎日のように目にし、「中国ビジネスはもう終わりなのだろうか?」と不安に感じていませんか。
一方で、「撤退しているのはごく一部だ」という声も聞こえてきて、一体どちらが本当の情報なのか分からなくなっているかもしれません。
この記事では、メディアが報じる断片的なニュースの裏側にある、中国撤退を選ぶ日本企業のリアルな実態を、公式データや具体的な事例をもとに、どこよりも分かりやすく多角的に解説します。
●この記事を読んでほしい人
- 「中国撤退」のニュースの真相を、感情論ではなく事実で知りたい人
- 今後の日本と中国の経済関係に関心があるビジネスパーソン
- メディアの情報に流されず、物事の本質を自分で見極めたい人
●この記事を読むメリット
- 「大量撤退」というイメージと、統計データとのギャップが理解できる
- 企業が撤退を決断する、経済・地政学・市場の3つのリアルな理由が分かる
- 撤退しないユニクロやトヨタの、具体的な逆転戦略を知ることができる
- 多くのメディアが報じない「撤退したくてもできない」中国特有の壁が分かる
- ニュースの裏側を読み解き、自分自身の判断軸を持つことができる
さあ、データと事例で読み解く、日本企業の対中戦略の最前線へGO!。
「日本企業の中国撤退」その実態は?データと本当の理由

- 「大量撤退」は本当?統計データが示す真実
- 経済・地政学・市場、3つの変化が撤退理由
- EV化で苦戦。自動車・小売業界の撤退事例
- 加速する「チャイナ・プラス・ワン」戦略とは
- メディア報道と現実のギャップに注意しよう
「大量撤退」は本当?統計データが示す真実
「日本企業の中国撤退が加速している」というニュースをよく見かけますが、本当にそうなのでしょうか。一方で、「撤退はごく一部だ」という声も聞かれます。実際のところ、公式なデータを見ると、単純な「大量撤退」とは言えない複雑な実態が浮かび上がってきます。
ピーク時よりは減少、しかし近年は増加傾向
帝国データバンクの調査によると、2024年時点で中国に進出している日本企業は13,034社です。この数は、進出ブームのピークだった2012年の14,394社に比べると、確かに1,360社少なくなっています。この数字だけを見ると、撤退が進んでいるように見えます。
しかし、もっと最近の動きに注目すると、違う側面が見えてきます。実は、コロナ禍で事業の見直しが進んだ2022年の12,706社と比べると、2024年には328社増えているのです。
撤退よりも多い「新規参入」という事実
なぜ企業数は増えているのでしょうか。それは、中国から事業を撤退したり、所在が分からなくなったりした企業が1,243社あった一方で、新たに中国で事業を始めた企業が1,571社あったからです。つまり、去る企業よりも新たに入ってくる企業の方が多かった、ということになります。
この状況は、一部の企業が中国市場に見切りをつける一方で、新たなチャンスを見出して挑戦する企業も存在し続けていることを示しています。
| 項目 | データ |
| 中国進出企業数(2024年) | 13,034社 |
| ピーク時(2012年)からの変化 | -1,360社 (9.4%減) |
| 直近2年(2022年比)の変化 | +328社 (純増) |
| 今後「撤退・移転」を計画 | わずか1.4% |
ほとんどの企業は事業を継続
さらに、日本貿易振興機構(JETRO)の調査は、この傾向を裏付けています。中国で事業を行っている日本企業に今後の展開を尋ねたところ、「第三国への移転や撤退を考えている」と答えた企業は、全体のわずか1.4%にとどまりました。
このように、統計データは「日本企業が一斉に中国から逃げ出している」というイメージとは少し違う現実を示しています。一部の企業が撤退する一方で、新たに挑戦する企業もおり、多くの企業は中国での事業を続けているのが現状なのです。
経済・地政学・市場、3つの変化が撤退理由
では、なぜ一部の日本企業は中国からの撤退を選ぶのでしょうか。その背景には、単一の理由ではなく、「経済」「地政学」「市場」という3つの大きな変化が複雑に絡み合っています。
理由1:経済的な魅力の低下
かつて日本企業を惹きつけた中国の経済的なメリットは、少しずつ薄れています。
- コストの上昇人件費がこの10年で大きく上昇し、「安価な労働力」という最大の魅力が失われました。「世界の工場」としての優位性が揺らいでいます。
- 現地企業との競争激化中国企業は技術力やマーケティング能力を飛躍的に向上させ、今や多くの分野で日本企業を上回る手ごわいライバルになっています。
- 国内市場の減速不動産不況などを背景に中国経済の成長が鈍化し、消費者の財布のひもが固くなっています。巨大市場という魅力そのものが、以前より輝きを失っている状況です。
理由2:地政学的なリスクの高まり
国際関係の緊張が、事業運営に直接的な影響を及ぼすようになりました。
- 米中対立の激化アメリカと中国の対立が深まる中で、両国とビジネスを行う日本企業は難しい立場に置かれています。サプライチェーンの見直し(デリスキング)を迫られるケースが増えています。
- 予測不能な法規制2023年に改正された「反スパイ法」は、定義が非常にあいまいです。そのため、通常の市場調査のようなビジネス活動が「スパイ行為」と見なされるのではないか、という懸念が生まれています。従業員の安全確保が、経営の新たな重要課題となっています。
理由3:市場そのものの急激な変化
中国市場の内部では、これまでの常識が通用しない、破壊的な変化が起きています。
- EV(電気自動車)革命中国政府の強力な後押しにより、自動車市場は急速にEVへとシフトしました。この急激な変化に、ガソリン車やハイブリッド車を得意としてきた日本の自動車メーカーの多くが乗り遅れてしまいました。
- Eコマースの支配アリババなどに代表されるネット通販や、ライブコマースといった新しい販売手法が消費の主役となりました。このデジタル化の波に対応できなかった百貨店などの従来型小売業は、厳しい状況に追い込まれています。
これら3つの課題はそれぞれが独立しているわけではありません。互いに影響し合い、日本企業に対して、これまでの中国戦略を根本から見直すことを迫っているのです。
EV化で苦戦。自動車・小売業界の撤退事例
先ほど解説した3つの大きな変化は、特に一般消費者を相手にするビジネス(B2C)を行う業界に大きな影響を与えています。ここでは、代表的な事例として自動車業界と小売業界の動きを見ていきましょう。
EVの波に乗り遅れた自動車業界
中国の自動車市場は、国を挙げたEV(電気自動車)シフトによって、市場のルールそのものが変わってしまいました。この変化に対応できなかった企業が、撤退や事業縮小を余儀なくされています。
- 三菱自動車(2023年に撤退)販売不振が深刻化し、2023年に中国での自動車生産から完全に撤退することを決定しました。EV化の急速な流れについていくことができませんでした。
- 日産自動車(工場閉鎖)完全な撤退ではないものの、2024年に江蘇省の工場を閉鎖しました。主力であったSUVが、価格競争力に優れる中国メーカーのEVやPHEVとの競争に敗れたことが大きな要因です。
- スズキ(2018年に撤退)比較的早い段階で撤退した事例です。得意としていた小型車市場が中国で縮小したことに加え、その後のEV化の流れにも対応できず、2018年に市場から去りました。
Eコマースに敗れた小売業界
ネット通販の爆発的な普及と、消費マインドの冷え込みは、従来型の店舗を構える小売業に大きな打撃を与えました。
- 三越伊勢丹(上海の店舗を閉鎖)30年以上にわたり中国で高品質なサービスを提供してきましたが、ネット通販との競争激化や消費の低迷には抗えませんでした。象徴的な存在だった上海の店舗も2024年に営業を終了し、中国事業を大幅に縮小しています。
- モスバーガー(中国本土から撤退)ハンバーガーチェーンのモスバーガーも、中国での個人消費の落ち込みを受け、2024年に本土の全店舗を閉店しました。今後の投資効果が見込めないと判断しました。
これらの事例から分かるのは、消費者の好みや市場のルールが急激に変わる中で、変化に対応できなかった企業が厳しい決断を迫られているという現実です。
加速する「チャイナ・プラス・ワン」戦略とは
中国事業のリスクが高まる中で、多くの日本企業が注目しているのが「チャイナ・プラス・ワン」という戦略です。これは、中国から完全に撤退するのではなく、中国の拠点に加えて、別の国にもう一つの生産拠点や調達網を設ける考え方を指します。
なぜ今「プラス・ワン」が必要なのか
この戦略が加速している背景には、これまで見てきたような複合的なリスクがあります。
- コストの上昇:中国国内の人件費などが上がり、生産拠点としてのコストメリットが薄れてきました。
- 地政学リスク:米中対立の激化により、中国で生産した製品がアメリカへの輸出時に高い関税をかけられるといったリスクが現実のものとなりました。
- 供給網の脆弱性:特定の国に依存しすぎることの危うさが、コロナ禍のロックダウンなどで明らかになりました。
これらのリスクを避けるため、中国だけに集中するのではなく、拠点を分散させる動きが活発になっているのです。
「プラス・ワン」の候補地はどこか
新たな投資先として、特にアジアの新興国が注目されています。
| 国・地域 | 主な魅力 |
| インド | 14億人を超える巨大な市場、高い経済成長への期待 |
| ベトナム | 中国に地理的に近い、比較的安価な人件費 |
| タイ | 自動車産業の集積地としての強固な基盤 |
| フィリピン | 英語が堪能な労働力を確保しやすい |
戦略に伴う新たな課題
しかし、この戦略は簡単な道のりではありません。新たな拠点には、中国とは異なる種類の課題が存在します。
- インフラが未整備(道路、港湾、電力など)
- 多くの企業が集中することによる人件費の高騰
- 現地の法制度や政治的な不安定さ
結局のところ、「チャイナ・プラス・ワン」は「脱中国」ではなく、「リスク分散(デリスキング)」と捉えるのが正確です。巨大な中国市場向けの生産は中国で続けつつ、他の国への輸出向け生産は「プラス・ワン」の拠点で行う、といった役割分担が進んでいます。
メディア報道と現実のギャップに注意しよう
ここまで見てきたように、「日本企業の中国撤退」というテーマは、一面的な情報だけでは実像を掴むのが難しい問題です。特に、メディアの報道に触れる際には少し注意が必要です。
なぜ「大量撤退」のイメージが広がるのか
企業の「撤退」や「工場閉鎖」は、具体的で分かりやすいため、ニュースになりやすい傾向があります。三菱自動車の撤退や三越伊勢丹の閉店といった大きな動きは、多くの人の印象に強く残ります。
しかし、その裏側で静かに進んでいる事業の再編や、地道に戦略を練り直している大多数の企業の姿は、なかなか報道されません。結果として、撤退する企業の動きばかりが目立ってしまい、「大量撤退が進んでいる」というイメージが広がりやすくなるのです。
バランスの取れた見方を持つための3つの視点
このテーマについて考えるとき、以下の3つの視点を持つと、よりバランスの取れた理解がしやすくなります。
- 撤退のニュースは「どの業界か」を見る自動車や小売など、特定の業界での動きが、日本企業全体の動きを代表しているわけではないことを理解することが大切です。
- 企業の「総数」の増減に注目する撤退する企業数だけでなく、新規参入する企業数も合わせて見ることで、より客観的な状況が見えてきます。
- 「事業継続」が多数派であることを忘れないごく少数の企業しか撤退を計画していないという統計データを念頭に置くと、報道から受ける印象が少し変わって見えるかもしれません。
「中国撤退」という強い言葉だけに注目するのではなく、その背景にある複雑な現実をデータや多角的な視点から見ることが、この問題を正しく理解するための鍵となります。
中国撤退しない日本企業の逆転戦略と「壁」

- ユニクロが実践する「超現地化」経営とは?
- トヨタが現地IT大手と提携に踏み切る理由
- 撤退とは無縁?好調なB2B企業の共通点
- なぜ撤退したくてもできない企業があるのか?
- 高額な補償金と複雑な行政手続きのリアル
ユニクロが実践する「超現地化」経営とは?
多くの企業が中国市場で苦戦する中、全く逆の戦略で成長を続ける企業もあります。その代表格が、アパレルブランドのユニクロです。ユニクロの成功の鍵は、「超現地化」とも呼べる徹底した経営戦略にあります。
グローバル標準から「個店経営」へ
ユニクロは、世界中で同じ商品を同じように売るという画一的な戦略から脱却し、「個店経営」を推し進めています。これは、一つひとつの店舗が、その地域の特性に合わせた運営を行うことです。
- 気候への対応:広大な中国では、北と南で気候が全く異なります。各店舗が地域の気候に合わせて商品の品揃えを最適化します。
- 顧客ニーズの反映:地域の文化や顧客層の好みを分析し、マーケティングや商品の見せ方を調整します。
このように、それぞれの店舗が地域に根差した存在になることを目指すことで、顧客との強い結びつきを生み出しています。
ブランド哲学「LifeWear」の発信を強化
ユニクロは単に商品を売るだけでなく、「LifeWear」というブランドの哲学を伝えることにも力を入れています。これは「あらゆる人の生活を、より豊かにするための服」という考え方です。
成長が見込める都市には大規模な旗艦店をオープンし、ブランドの世界観を体験できる空間を提供しています。これにより、「安くて品質が良い」という価値だけでなく、ブランドそのものへの共感や信頼を育んでいるのです。
逆風の中でも積極的な出店を継続
消費マインドが冷え込んでいると言われる中でも、ユニクロは中国での事業拡大に意欲的です。不採算店舗の整理は進める一方で、年間50〜80店舗というペースで新規出店を継続しています。
将来的には、中国大陸・香港・台湾を合わせたグレーターチャイナ地域で3,000店舗体制を築くという、非常に野心的な目標を掲げています。この姿勢は、短期的な市場の変動に左右されない、長期的な視点でのコミットメントを示しています。
トヨタが現地IT大手と提携に踏み切る理由
中国でEV(電気自動車)への移行に出遅れ、苦戦を強いられたトヨタ自動車は、自社単独で開発を進める「自前主義」から、現地の巨大IT企業と積極的に手を組む戦略へと大きく舵を切りました。この決断の背景には、中国市場の独特なスピード感と消費者のニーズに迅速に応えるという、強い危機感があります。
惨敗から学んだ「中国の現実」
トヨタが当初投入したEVは、中国市場で消費者の心をつかむことができませんでした。その最大の理由は、中国の消費者がEVに求める「スマート化」のレベルが、日本のメーカーの想定をはるかに超えていたからです。
中国では、車は単なる移動手段ではなく、「スマートデバイス」として捉えられています。そのため、以下のような機能が重視されます。
- 優れた音声認識:エアコンの操作から複雑な会話まで、AIアシスタントが自然に対応すること。
- 多彩なアプリ連携:車内で動画を見たり、買い物をしたりと、スマートフォンと同じような体験ができること。
- 高度な運転支援:最新の地図情報と連携し、スムーズな自動駐車や渋滞時の運転サポートを実現すること。
これらの分野は、まさに中国のIT企業が最も得意とするところです。トヨタは、自社だけでこの開発スピードに追いつくのは不可能だと判断し、現地のトップ企業と提携する道を選びました。
目的別のパートナーシップ
トヨタは、それぞれの分野で強みを持つ中国IT大手と、目的別に提携を進めています。
| 提携先企業 | 主な提携内容 |
| ファーウェイ(華為技術) | スマートコックピットの頭脳となる車載OS「HarmonyOS」や、AI音声アシスタントを共同開発。 |
| テンセント(騰訊) | AI、ビッグデータ、クラウド技術を活用し、利用者の体験価値を高めるサービスを共同で創造。 |
| Momenta | 高度な運転支援システムや自動運転技術の開発で協力。 |
「中国のため、中国で創る」新体制
トヨタの戦略転換は、単に技術を導入するだけにとどまりません。開発の考え方そのものを「日本中心」から「中国中心」へと転換しています。
中国人エンジニアが開発の主導権を握る「リージョナル・チーフ・エンジニア」制度を導入し、現地のニーズを製品開発に直接反映させる体制を強化しました。これは、「中国の消費者のための車を、中国の知恵を借りて創る」という、トヨタの新たな決意の表れです。
かつての成功体験を捨て、現地の最先端技術を柔軟に取り入れるトヨタの戦略は、厳しい中国市場で生き残りをかける日本企業の、象徴的な動きと言えるでしょう。
撤退とは無縁?好調なB2B企業の共通点
これまで紹介した自動車やアパレル業界とは対照的に、中国からの撤退とは無縁で、むしろ投資を拡大している分野があります。それは、企業を相手にビジネスを行うB2B(Business-to-Business)企業、特に、高度な技術力を持つ電子部品メーカーなどです。
なぜB2B企業は好調なのか
B2B企業が好調な理由は、一般消費者の動向や現地の小売企業との競争に直接さらされることが少ないためです。B2B企業の顧客は他の企業であり、その成功は中国の製造業全体の強さに直結しています。
特に、中国の先進的な産業エコシステム(生態系)に深く組み込まれ、重要な部品を供給している企業は、中国市場での存在感を高めています。
事例:村田製作所の巨額投資
その代表例が、電子部品大手の村田製作所です。
村田製作所は2022年、約445億円を投じて中国・無錫市に新たな生産工場を建設すると発表しました。村田製作所が作る積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、スマートフォンやEV(電気自動車)に無くてはならない基幹部品です。
中国は、スマートフォンとEVの世界最大の生産国です。つまり、日本の自動車メーカーが苦戦しているEV市場や、競争が激しいスマホ市場で躍進する中国企業に部品を供給することで、村田製作所は共に成長するという戦略をとっているのです。
B2B企業に共通する戦略
好調なB2B企業には、以下のような共通点が見られます。
- 代替不可能な技術力中国企業が簡単には真似できない、高品質で専門的な部品や素材を供給する技術を持っています。
- 中国の産業エコシステムへの統合顧客であるメーカーの工場が集まる地域に生産拠点を構え、サプライチェーンの重要な一部を担っています。
- 中国企業の成長を自社の成長に中国のハイテク企業が成長すればするほど、自社の部品の需要も増えるという、共存共栄のビジネスモデルを確立しています。
このように、「日本企業の中国撤退」という話は、主に消費者向けビジネス(B2C)の側面が強いと言えます。一方で、中国の製造業を根幹で支えるB2B企業にとっては、中国は依然として非常に重要な、そして成長を続ける市場なのです。
なぜ撤退したくてもできない企業があるのか?
中国での事業が厳しくなっても、すぐに撤退という決断ができない日本企業は少なくありません。その背景には、「撤退したくても、できない」という中国特有の高い壁が存在します。
会社を畳むという点では日本と同じように見えますが、その手続きの複雑さや求められるコストは、日本での常識とは大きく異なります。
迷宮のような法務・行政手続き
中国で会社を清算するには、まず複数の行政機関から許可を得る必要があります。
- 複雑な許認可プロセス会社の解散には、商務部門、市場監督管理部門、税務部門、外貨管理部門など、多くの役所の承認が求められます。これらの手続きは連携しているため、一つが滞ると全てのプロセスが止まってしまいます。
- 厳しい税務調査撤退する企業に対しては、特に厳しい税務調査が行われる傾向があります。過去の申告内容を徹底的に調べられ、多額の追徴課税を求められるケースも珍しくありません。
これらの手続きは、順調に進んだとしても数年単位の時間がかかることがあり、企業にとっては大きな負担となります。
資産を売るという高いハードル
工場や設備などの資産を処分することも、撤退を難しくする大きな要因です。
- 買い手を見つける困難さそもそも、会社の事業や資産を適正な価格で買ってくれる相手を見つけること自体が、景気後退の局面では非常に困難です。
- 土地使用権の制約中国では土地の所有権は国家にあり、企業が持つのは「土地使用権」です。この権利を売却するには地方政府の許可が必要で、政府の意向によっては売却がスムーズに進まないことがあります。
最大の障壁:従業員への経済補償金
多くの場合、撤退における最大の壁となるのが、従業員の解雇に伴う問題です。
中国の法律では、会社都合で従業員を解雇する場合、勤続年数に応じた「経済補償金」を支払うことが義務付けられています。基準は「勤続1年につき1ヶ月分の給与」ですが、実務上、この法定金額だけで円満に解決することはほとんど不可能です。
| 補償金の内訳 | 内容 |
| 法定経済補償金 | 法律で定められた最低限の支払い。(勤続年数×月給) |
| 上乗せの割増金 | 円満な解決のため、法定額に「+α」で支払うことが慣行となっている。 |
| その他の手当 | 交渉によっては、慰労金や就業支援金などが追加される場合もある。 |
長年操業してきた大規模な工場の場合、この経済補償金の総額は、会社の財務を揺るがすほどの巨額に膨れ上がる可能性があります。
これらの「法務」「資産」「労務」に関する高いハードルが、業績が悪化しても撤退に踏み切れない「ロックイン(閉じ込め)効果」を生み出しているのです。
高額な補償金と複雑な行政手続きのリアル
前のセクションで触れた「撤退の壁」について、ここでは特に大きな問題となる「従業員への経済補償金」と「行政手続き」のリアルな姿を、もう少し詳しく見ていきましょう。
「N+1」では済まない経済補償金の実態
中国の法律で定められた経済補償金は、勤続年数(N)に応じた月給分、つまり「N」が基本です。しかし、従業員との交渉を円満に進め、ストライキなどの労働争議を避けるためには、この法定基準に上乗せした金額を支払うのが一般的になっています。
この上乗せ分は「N+1」と呼ばれることもありますが、実際にはそれ以上の支払いを求められるケースも少なくありません。
- 近隣の事例が基準になる従業員は、近隣の工場が過去に支払った補償金の水準を把握していることが多く、その金額が事実上の交渉のスタートラインになります。
- 交渉を専門とする弁護士の存在中国では労働紛争を専門に扱う弁護士が多く、従業員が弁護士を立てて、法的な観点からより有利な条件を引き出そうと交渉してくることも珍しくありません。
- SNSでの称賛が新たな基準に2022年にキヤノンが広東省の工場を閉鎖した際には、法律の規定を大幅に上回る手厚い補償金を支払ったことが、中国のSNSで「良心的な企業」として称賛されました。しかし、このような事例が新たな「相場」となり、他の企業が撤退する際のプレッシャーになるという側面もあります。
ゴールの見えない行政手続きの連鎖
会社の清算手続きも、日本のように決められた手順通りに進むとは限りません。各行政機関には大きな裁量権があり、一つ一つのプロセスが交渉の連続となります。
以下は、撤退手続きの一般的な流れですが、各段階で想定外の遅延が発生する可能性があります。
- 解散決議と清算委員会の設置まず社内で会社の解散を正式に決定します。
- 行政機関への届け出商務部門や市場監督管理部門などに解散を届け出ます。ここからが長い手続きの始まりです。
- 税務・税関の完結手続き最も時間がかかると言われるプロセスです。過去の税務申告を厳しくチェックされ、見解の相違があれば交渉が必要になります。
- 銀行口座の閉鎖・外貨送金許可全ての債務を清算した後、最後に残った資金を日本に送金しますが、この外貨の持ち出しにも外貨管理部門の許可が必要です。
- 登記抹消全ての許可を得て、ようやく会社の登記を抹消できます。
地方政府によっては、雇用や税収が失われることを嫌い、手続きを意図的に遅らせるようなケースも見られます。このように、撤-退のプロセスは多額の費用と数年単位の時間を要する、まさに「体力勝負」なのです。
まとめ:中国撤退をめぐる日本企業のリアルと今後の見方
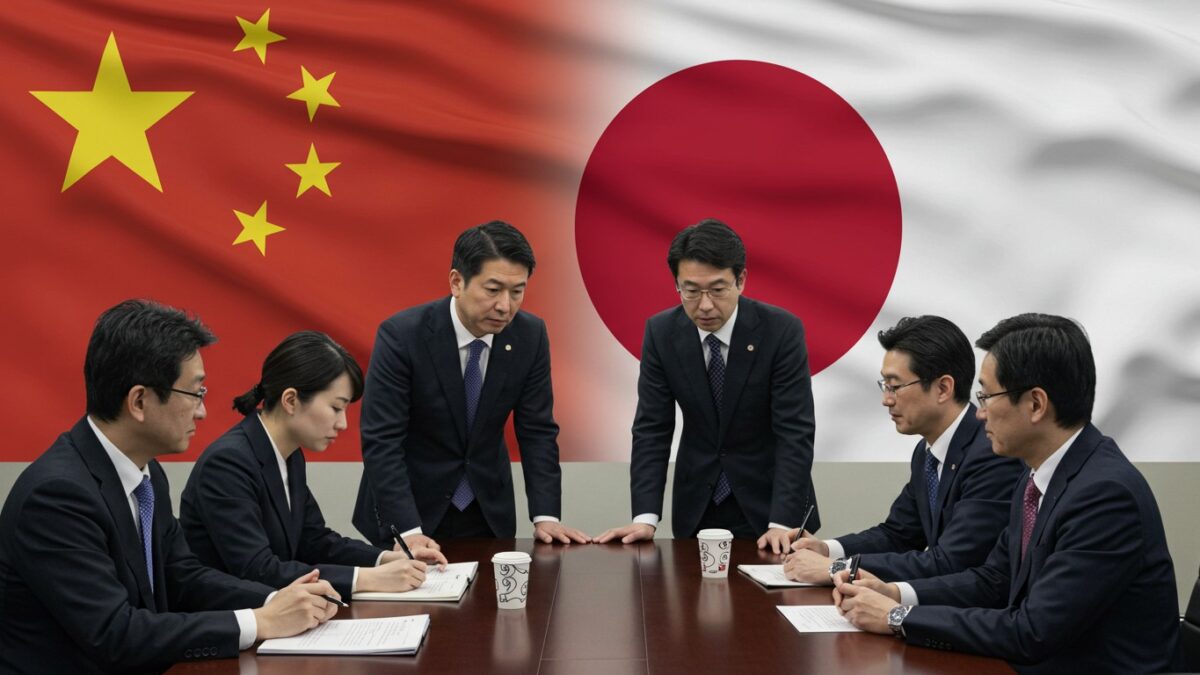
記事のポイント
- 統計上、日本企業の「大量撤退」は起きていない
- 撤退企業を上回る数の新規参入企業が存在する
- 撤退の主な理由は経済・地政学・市場の複合的変化である
- 特に自動車や小売業界など消費者向けビジネスで撤退が目立つ
- リスク分散のための「チャイナ・プラス・ワン」戦略が加速している
- ユニクロは「超現地化」戦略で厳しい市場に適応している
- トヨタは現地IT大手との提携でEV化の遅れを挽回しようとしている
- 好調なB2B企業は中国の産業エコシステムに深く関わっている
- 多くの企業は撤退したくてもできない中国特有の事情を抱える
- 高額な従業員補償金と複雑な行政手続きが撤退の大きな壁である
総括
「中国撤退に踏み切る日本企業」というニュースは、多くの関心を集めます。しかし、この記事を通して、その言葉の裏にある複雑な実情が見えてきたのではないでしょうか。
統計データが示すように、撤退する企業がいる一方で、新たに挑戦する企業や、ユニクロやトヨタのように戦略を大胆に変えて市場に適応しようとする企業も確かに存在します。また、「撤退したくてもできない」という中国特有の根深い課題があることも、この問題を理解する上で欠かせない視点です。
今後、中国撤退を選ぶ日本企業に関するニュースに触れた際には、その背景にどのような個別事情があるのか、そして留まる企業はどのような戦略を描いているのか、という両面から考えることで、より深く日本と中国の経済関係を読み解くことができるでしょう。
本記事が、「大量撤退」という一面的なイメージだけでなく、多角的な事実を知る一助となれば幸いです。

